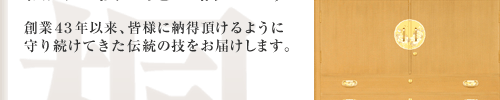

- TEL
- :052-444-1402
- 所在地
- 愛知県海部郡美和町篠田乙柳53-1



三長家具は40年以上続く伝統技術を屈指し、流行に左右されず永く愛される桐たんすを造っています。また現代の生活様式の多様化に柔軟に対応した桐たんす造りを進めています。私したちの製造した桐たんすは中部地方中心に家具専門店、百貨店、家具問屋などの店頭にて販売されています。各地方のお客様の声(たんすのデザイン、造り、価格など)を聞き、製品造りに励んでいます。
職人の自己満足でたんすを造ってもお客様のためにならない(価格、デザイン)。私したちはお客様のご要望に応じて最高の技術、技法を用いて桐たんすを造ります。名古屋地区では唯一総桐たんすの製造元です。

桐の木が桐箪笥になるまでにはとても長い年月を要します。伐採した桐の木はまず私たちの乾燥場で丸太で6ヶ月から1年寝かせます。これは桐の木を落ち着かせ名古屋の環境に慣れさせるためです。
そして製材された桐板材は天日にて約2年間アクを抜きながら自然乾燥させます。桐板材が真っ黒になりアクが抜けたことを確認し屋内にしまい半年から一年寝かせます。そして、「狂い直し」といい板のそりやひずみを火であぶりまっすぐに直し職人たちの厳しい目で選別され上質な桐材だけを使います。
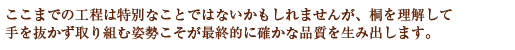

こうして桐の選定から仕上げに至るまですべて自社で行います。とくに初工程のアク抜き乾燥期間を短縮した桐(人工乾燥、漂白剤によるアク抜き)はいくら良材でも長く使えばその差は歴然です。※補足 上記のアク抜きという作業をやることによって 品質がよくなります。やらない製造業者もあるので 気をつけて下さい。
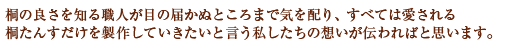

桐たんす造りはすべて手作業、手加工で行い40年以上にわたって培ってきた経験を活かし 独自の技術で長年愛用してきた道具と共に何十工程にも及ぶ匠の技で一棹一棹丁寧に 想いを込めて造り、末永く愛されお使いいただきたいという私たちの想いが託されています。
 初工程の木取りは各部材の寸法に合わせ
初工程の木取りは各部材の寸法に合わせ 接合部の強度を増すために蟻組といい
接合部の強度を増すために蟻組といい 蟻組をして底板を打った引出しは箪笥本体の
蟻組をして底板を打った引出しは箪笥本体の 木地の表面に水を塗り、へこんだ箇所を
木地の表面に水を塗り、へこんだ箇所を 最終仕上げは金具付け。引き手や前飾りの
最終仕上げは金具付け。引き手や前飾りのCopyright (C) 2009 尾張・名古屋の桐たんす . All rights reserved.presented by アイテムプレス