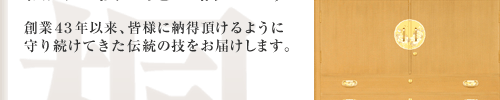

- TEL
- :052-444-1402
- 所在地
- 愛知県海部郡美和町篠田乙柳53-1


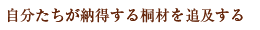
製材された桐材を求める職人がほとんどのなか、山へ出向き樵(きこり)と会話し、山に入り自然の状況を把握してきます。地球温暖化の中、良い桐が少なくなっています。適材適所に大切に桐材を使います。
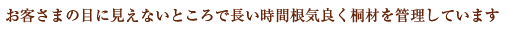

何十年使っても「良いたんすだね」と言われるには天然桐材の大敵である渋抜き、乾燥は非常に大切なことと思います。いくら職人の腕が良くてもたんすを購入後数年で変色や乾燥不十分で不具合が生じたりしては何もなりません。私したちはまず製材する事から始めます。良質な材料にするため丸太を挽く時は非常に神経を使います。挽き角度を誤ると良質な木目がでません。

そして製材された桐板材を板干し場で桟状乾棚に噛まし1枚1枚丁寧に干します。そして1年〜2年位、二梅雨も雨風にさらし、渋抜を促進させ自然乾燥させます。また、乾燥期間中は桐板材の天地(上下)、左右を差し換え満遍なく日光、雨、風があたるようにします。渋抜乾燥は桐材の伸縮及び狂いを少なくし、製品化した桐の渋による変色を防ぎます。こうして桐箪笥を造り始める前に私したちは桐材を最高の状態にしています。



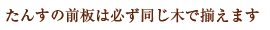
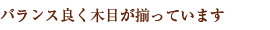

Copyright (C) 2009 尾張・名古屋の桐たんす . All rights reserved.presented by アイテムプレス